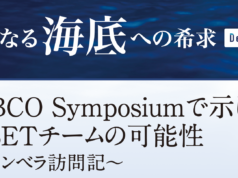四方を海に囲まれ、水産資源に恵まれる日本列島。この資源の生産と再生の場として重要な働きを担うのが、陸地を囲むようにして広がる“藻場”の存在だ。海藻が繁茂し、海の森とも呼ばれる藻場は、海域や水深、底質などによってその特徴が異なる。今回は、海洋生物資源のモニタリングに取り組む島根大学エスチュアリー研究センターの南憲吏氏にお話を伺った。

◆ 藻場は海洋生物たちのゆりかご
沿岸域の海洋生態系や漁業を考えるにあたり、藻場の存在は欠かせない。海洋生物にとっては、繁殖場、隠れ場、餌場であり、人間にとっては水産資源の生産と再生の場としての役割を担う。また、水中の有機物を分解したり、炭酸ガスを吸収したり、酸素を供給したりと海中の物質循環にも寄与している。しかし、近年の地球規模での環境の変化により、藻場が減少しているとの報告が相次いでいる。富栄養化によって植物プランクトンが増殖し、水の透明度が低下すると、光合成によって生育する海藻、海草は生育を制限されてしまう。人の暮らしが藻場を侵食しているのだ。この傾向は日本でも顕著だ。四方を海に囲まれる日本においては、沿岸域を住宅地域、工業地域、商業地域として活用せざるを得ない。日本の藻場として特に代表的なものはアマモ場、アラメ・カジメ場、ガラモ場、コンブ場の4タイプであるが、水産庁の報告によれば瀬戸内海ではアマモ場が30年間の内に70%も減少したという。未来に渡り豊かな海洋生態系を維持しつつ人間活動を行っていくためには、沿岸資源の分布を正しく捉え、その特徴や変遷を評価することが必要なのだ。

◆ 見える化することで資源を守る
「海の中に広がる海洋資源は、一見して状態を把握することができません。見えないものをどうやって保護・維持するか議論しても、なかなか実感が伴わないものです」。大切な資源を維持管理していくためには、きちんと状態を知り、共通認識が可能な方法で評価を行うことが重要だと南氏は話す。従来、沿岸域の生物分布を推定する方法としては、海に潜って肉眼で状態を観察するといった直接的な手法が一般的であったという。生育状態や種判別など詳細な情報を得ることができる一方で、多大な労力や時間がかかり広範囲を対象とした調査は極めて困難であった。そこで南氏らは、広範囲な対象生物の分布を連続的かつ定量的に取得することができる、計量魚群探知機を用いた音響的なモニタリング手法に取り組んでいる。南氏らの方法は、水中に超音波を発射し、対象物の固有の音響反射強度を計測する仕組みだ。これにより対象物の有無、深度、生物量などを推定することが可能になる。しかし、この推定に必須となる一個体あたりの音響反射強度(ターゲットストレングス)は魚種によって大きく異なり、かつ測定データの蓄積が進んでいない。南 氏はこの計量魚群探知機を用いた生物資源の分布調査を沿岸部に適用し、知見を蓄積してきた。2015年から新たにターゲットストレングスの測定を行った魚種はサケ、マアジ、ハタハタ、スルメイカ、マダイ等。よく耳にする主要な魚種でさえ、これまで計測できていなかった事実から、海洋における測定技術において広域な未開発領域が存在することがわかる。

◆ 技術革新がもたらす資源管理の新常識
さらに南氏らは同様の手法を藻場にも適用することで、資源分布を見える化することに成功している。知床半島の東沿岸に連続的に広がるコンブ場の調査では、コンブ漁の前後で資源分布がどのように変動しているかを明らかにし、長期的に定点観測を行うことで、人間活動の影響を評価する道筋を示すことができた。今後、新型ソナーの開発や沿岸域の海底地形図が気軽に利用可能な水準にまで到達することで、生物資源モニタリングの現状は大きく変わるだろうと予測される。「計測手法が発達することで、調査の効率は格段に向上するでしょう」。南氏はソナー開発を進める研究チームともコミュニケーションを密にしながら、最新技術の導入も視野に入れて、生物資源管理のスタンダードとなりうる手法を模索し続けている。資源管理技術の進歩は、沿岸域での漁業効率を大いに向上させるであろうと期待が高まる。しかし、この豊かな海洋資源を次の時代へとつなぐため、持続可能な資源循環のしくみを整えていくことも忘れてはならない。(文・中嶋 香織)
記事掲載:研究応援vol.11 P14−P15